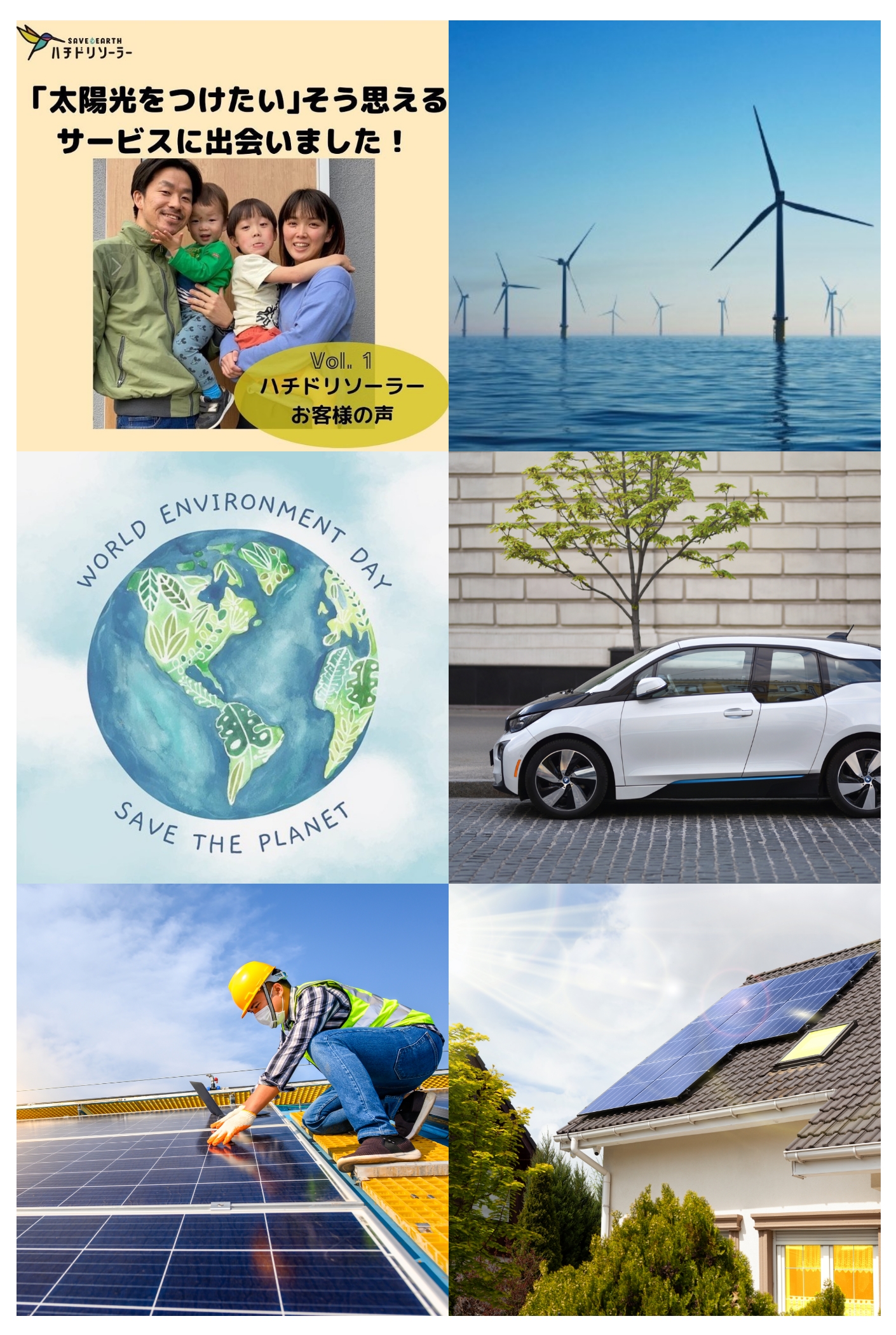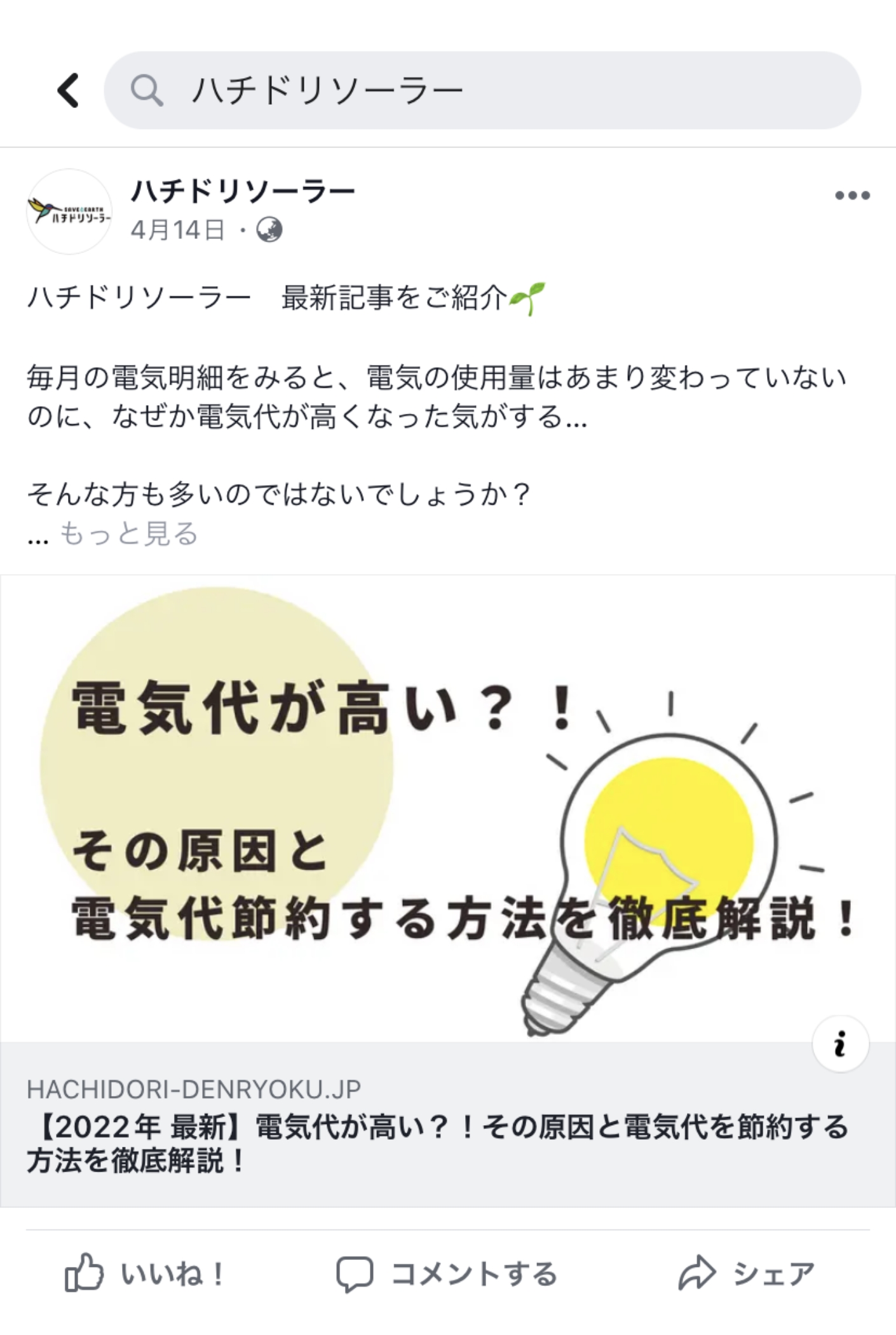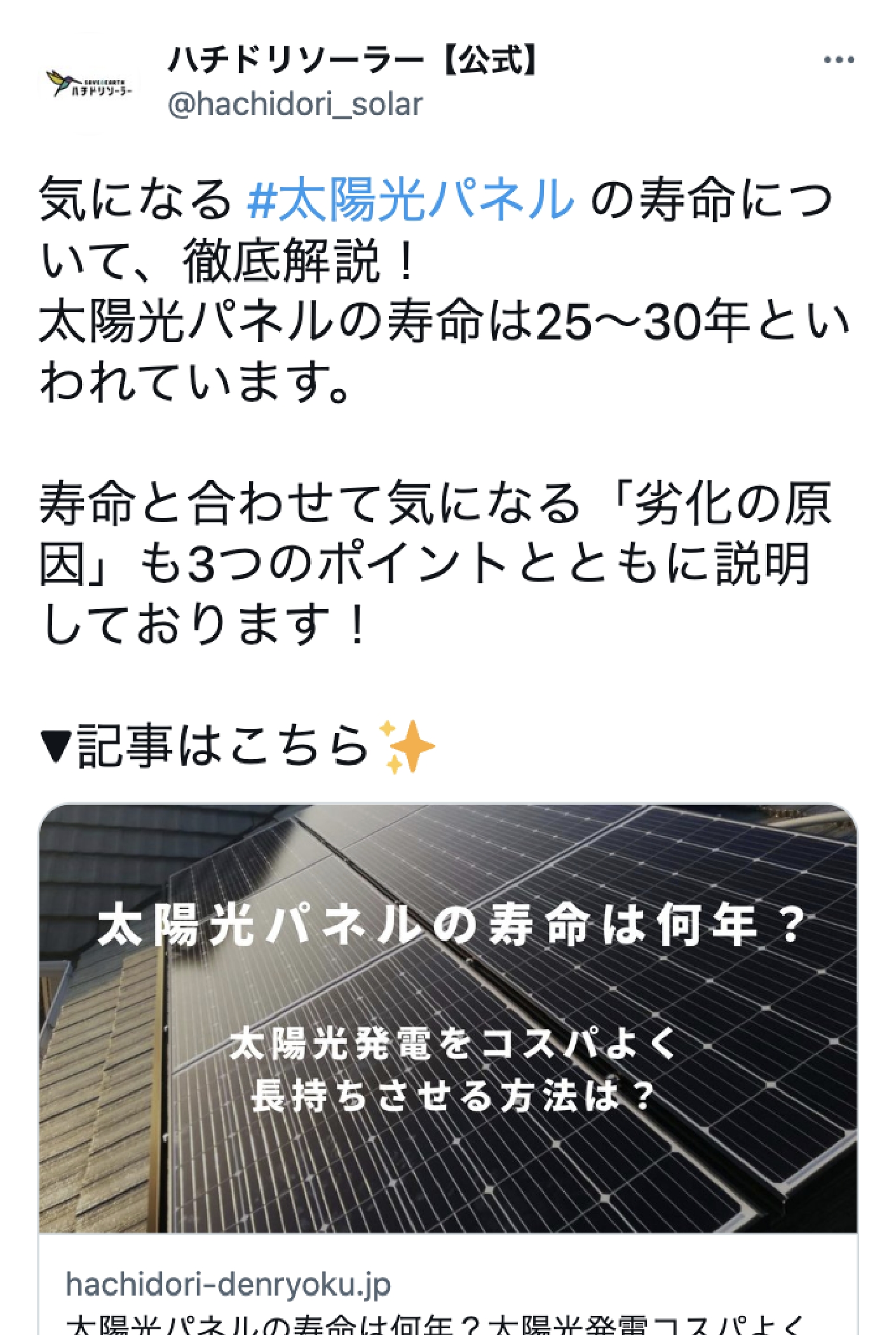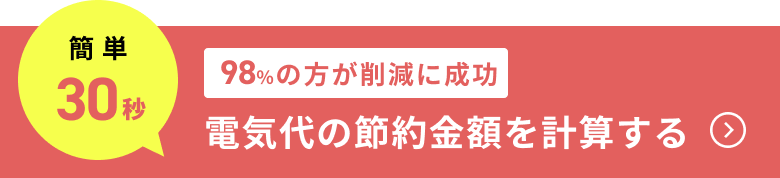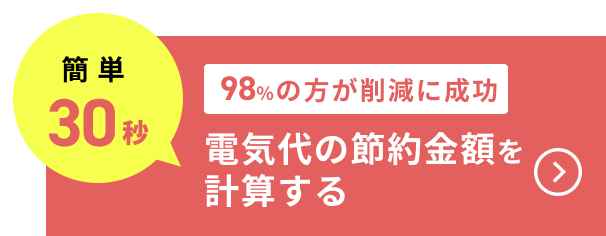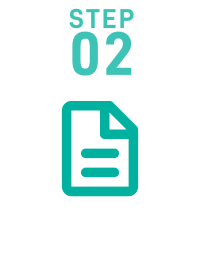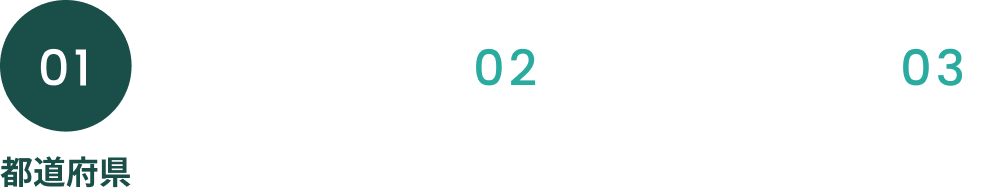家庭用蓄電池の容量の決め方とは?目的別の選び方や計算方法を徹底解説
この記事は2025/08/08に更新されています。
家庭用蓄電池の導入を検討する際、最も重要な要素のひとつが「蓄電容量(kWh)」です。蓄電池の容量が小さすぎると期待した効果が得られない一方で、容量が必要以上に大きすぎると初期費用が無駄にかかってしまいます。
そのため、家庭用蓄電池は自身のライフスタイルやソーラーパネルの発電状況など、環境に見合った容量の選び方が重要です。また、太陽光発電システムとの連携や災害への備えなど、導入目的によって最適な容量は異なります。
この記事では、蓄電池導入のメリット・デメリットを整理したうえで、ご自身の目的やライフスタイルに合った蓄電池容量を判断するための具体的な計算方法や選定ポイントを分かりやすく解説します。
\\初期費用0円で始められる!//
太陽光・蓄電池・V2Hの導入から運用~メンテナンスまでプロが徹底的にサポート!
家庭用蓄電池の容量を選ぶ前のポイント!種類の違いを解説
家庭用蓄電池の容量を選ぶ前に、「kWとkWh」「定格容量/実効容量」「全負荷型/特定負荷型」「100V/200V」などの違いに着目することが重要です。
kWとkWhの違い
「kW(キロワット)」と「kWh(キロワット時)」は、エネルギーと電力を測定するために使用される単位ですが、それぞれ異なります。
- kW(キロワット) は電力の単位であり、一定の時間内に使用される電力の量を示します。電気機器の消費電力や発電設備の発電能力を示す際に用います。1kWは1000ワットに相当します。
- kWh(キロワット時) はエネルギーの単位で、電力が一定時間にわたって使用された総量を示します。電気使用量や蓄電池の容量を表すのに用いられます。例えば、1kWの電力を1時間使用した場合、1kWhのエネルギーを使用したことになります。
簡単に言うと、kWは「その瞬間にどれだけの電力が使用されているか」を示し、kWhは「ある期間においてどれだけのエネルギーが使用されたか」を示します。蓄電池においては、kWは放電や充電の際の電力量を、kWhは蓄電池が保持している総エネルギー量をそれぞれ表します。
定格容量/実効容量の違い
定格容量とは、蓄電池がどれだけの電気の「量」を貯められるかを示す単位です。この数値が大きいほど、長時間の電力供給や多くの電力消費に対応できます。
ただし、カタログなどに記載される定格容量と、実際にご自宅で利用できる実効容量で容量に若干の違いがある点に注意が必要です。バッテリー寿命を伸ばすため過放電などを防ぐ施策が取り入れられているため、通常はカタログ等の定格容量よりも10~20%ほど実際に使える容量が少なくなります。
そのため、蓄電池の容量を比較検討する際は実効容量を基準にすることが重要です。
全負荷型/特定負荷型の違い
一口に家庭用蓄電池といっても、停電発生時などで家庭内のコンセントをどの程度までカバーできるかは環境によって異なります。
全負荷型は、停電発生時に分電盤を通してご自宅全体のコンセントをカバーすることが可能な蓄電池です。家中のほとんどの家電へ電力を供給でき、災害などで停電した際も普段と変わらない生活を送れます。蓄電池の容量を快適さで選びたい場合は、全負荷型がおすすめです。
特定負荷型は、事前に指定した特定のコンセントでのみ電力を供給できる蓄電池です。リビングのコンセントや照明、冷蔵庫など重要なポイントのみ電力を供給するため、消費電力量を抑えて長く活用できます。価格自体も比較的安価に導入できるメリットがある一方で、停電時に使える電気の範囲が限定されるのがネックです。
100V/200Vの違い
日本の家庭用電力には100Vと200Vがあります。一昔前ではほとんどが100Vでしたが、近年では200Vを取り入れた家電も増加傾向にあります。照明や多くの家電は100Vですが、エアコン、IHクッキングヒーター、エコキュートなどは200Vの電力が必要です。
そのため、200Vの機器を使用したい場合は、200V出力に対応した蓄電池を選択しなければなりません。特に全負荷型などを選択する場合は、制限やトラブルを最小限に抑えるためにも200V出力対応の蓄電池がおすすめです。
ただし、200V機器は消費電力が多いため、蓄電池の電力消費が増加します。
家庭用蓄電池の容量はどう決める?
家庭用蓄電池の導入を検討する際、「どの容量を選べばいいのか?」はもっとも悩ましいポイントです。容量選びを間違えると、停電時に十分な電力が確保できなかったり、逆に無駄なコストをかけてしまったりするため、慎重な判断が求められます。
家庭用蓄電池の容量を決める際は、以下の3つ選び方が重要です。
- 日常の電気使用量
- 太陽光発電システムの発電量(導入済みの場合)
- 非常時(停電時)の必要電力
日常の電気使用量を把握する
家庭用蓄電池の容量選定においてもっとも重要なのは、日々の電気使用量の把握です。電力会社の請求書やWeb明細から1日あたりの平均使用量(kWh)を確認しましょう。さらに、エアコンや暖房機器の使用が増える夏季・冬季のピーク時も考慮する必要があります。
たとえば、3人家族で1日平均10kWhを消費している場合、蓄電池の実効容量は最低でもこの数値をカバーできる選び方が望ましいです。季節変動が大きい地域では、冬場の最大使用量に合わせて容量を設定すれば、容量不足によるリスクを回避できます。
太陽光発電システムの発電量を考慮する
太陽光発電を導入している場合、蓄電池容量の選び方は「発電量と自家消費量のバランス」が比較検討のポイントです。昼間に消費しきれず、余剰となる電力を蓄電池に充電する運用が一般的となります。
たとえば、太陽光パネルの出力が4.5kWで、1日平均発電量が13.5kWhの場合、昼間の自家消費分を差し引いた余剰電力量が、蓄電池にためるべき容量の目安となります。一般的に自家消費率は30%と言われているため、日中に消費する4.05kWhを除いた約9kWh前後の蓄電池が効率的です。
とはいえ、夜間の消費量を大きく上回る蓄電池容量を確保しても、コストパフォーマンスの悪化を招いてしまいます。まずは日常の電気使用量を把握しておき、ピーク時を含めて1kWhほど実効容量に余裕のある蓄電池を選ぶと、ストレスフリーの生活に近づけることが可能です。
太陽光発電の発電量が多い家庭では、余剰電力を無駄なく活用できる容量を選定すれば、経済性と効率性を両立できます。
非常時(停電時)の必要電力量を逆算する
停電時にどの家電をどれだけの時間使いたいかを具体的にリストアップし、必要な電力量を算出するのも、蓄電池容量の選び方のひとつです。
たとえば、「冷蔵庫(200W)、照明(50W×2)、スマートフォン充電(10W)」を12時間稼働させたい場合、「合計消費電力は200W+100W+10W=310W」となります。
つまり、必要容量は310W×12時間÷1000=3.72kWh(容量)が家庭用蓄電池容量の目安です。この数値を基準に、実効容量で余裕を持たせた蓄電池を選ぶことが推奨されます。特に全負荷型(家全体に給電)を選ぶ場合は、200V対応家電の消費電力も考慮し、容量が早く減るリスクも念頭に置く必要があります
蓄電池を導入するメリット・デメリット

太陽光パネルの導入だけでも通常使用している電気の30%~40%ほどを賄えます。そこに蓄電池を導入すれば、自家消費率70%〜80%以上をカバーできるため、ほとんど電気を購入しない生活を送れるのが大きな魅力です。
また、通常太陽光発電は太陽光パネルが発電する日中(8時から17時)のみ電気を使用できますが、そこに蓄電池を設置すれば、夜間も太陽光の電気を活用できるようになります。
そのような太陽光発電に蓄電池を設置する主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット:停電時や災害時にも電気が使用できる
太陽光発電システムと蓄電池をセットで導入すれば、災害時や停電時でもいつも通り電気を使えます。
小さいお子さまがいるご家族やペットを飼われている方は、災害時でも避難所ではなく自宅で過ごしたい方が多いでしょう。そのような方には、太陽光発電と蓄電池の導入がおすすめです。
日常の生活をカバーできる容量の家庭用蓄電池を選ぶと、快適な生活を送れます。
メリット:電気代が安くなる
蓄電池を導入すれば、電力会社から購入する電気量が削減されます。昨今の電気代高騰の影響を受けるリスクが減り、使用する電気の量が変わらなくても電気代の削減に繋がります。
メリット:環境に配慮した生活が送れる
日本の電力発電は7割〜8割を火力発電に頼っています。火力発電は発電時に温室効果ガスを発生させるため地球環境に悪影響を及ぼします。
太陽光発電に蓄電池を設置して電力会社から購入する電気を節電すれば、火力発電に頼る割合が減少するため温室効果ガスを削減できます。環境を大切にしながら生活を送りたい方にも蓄電池の設置はおすすめです!
出典:経済産業省「今後の火力政策について」
デメリット:貯められる電気の量が決まっている
蓄電池は容量によって貯められる電気の量が決まっています。設置した蓄電池の容量が小さい場合、昼間に貯められる電気量が少なく夜間や曇りの日の電気をすべて補えません。
そのため、蓄電池を購入の際は容量不足に困らないように、あらかじめ、自宅での電気使用量を把握した上で適切な容量を設置する必要があります。
デメリット:充電できる回数に寿命がある
蓄電池には太陽光発電同様にサイクル数(寿命)があります。一般的な蓄電池の場合、寿命は6,000~12,000回が一般的(10~15年相当)とされます。太陽光発電の平均的な寿命は20年〜30年程度とされるため、太陽光発電の寿命までに1度買い換えなければならないことがあります。
蓄電池の寿命は蓄電サイクル(蓄電池内の電力残量が100%の満充電から残量0%の完全放電まで行った回数)で決まります。蓄電サイクルは設置する蓄電池の性能によって異なるため、あらかじめ蓄電サイクルが長い商品を選ぶことで長持ちさせられます。
使い方を工夫することで寿命を長持ちさせることに繋がりますし、最近では20年保証付きの蓄電池も販売されています。
デメリット:設置のスペースが必要
蓄電池の大きさは設置容量によっても異なりますが、おおよそエアコンの室外機ほどのスペースを用意する必要があります。また、「直射日光が当たらない」「高温や低温になりすぎない」「重塩害地域でない」などの設置条件にあうスペースを確保しなければならない点もデメリットです。
蓄電池を屋内に設置を検討している場合、多少の音が発生するためベッドルームなど、静かに過ごしたい部屋への設置は避けるようにしましょう。
ハチドリソーラーではコンパクトなサイズの蓄電池を標準でお取り扱いしているので、設置に必要なスペースはさほど大きくありません。
\\初期費用0円で始められる!//
太陽光・蓄電池・V2Hの導入から運用~メンテナンスまでプロが徹底的にサポート!
家庭用蓄電池選びで容量以外に注目すべきポイント
家庭用蓄電池の導入では、容量だけでなく「実用性」「耐久性」「将来性」を総合的に判断する必要があります。家庭用蓄電池は利用者一人ひとりの環境に応じてベストな容量を選ぶ必要がある一方で、いくつかチェックすべき条件は共通しています。
ここでは、容量以外に注目すべきポイントや注意点について解説します。
出力性能と電圧対応:使える家電が変わる
定格出力(kW)は同時に動かせる家電の総電力量を決定します。200V対応の全負荷型ならIHクッキングヒーター(3kW)とエアコン(2kW)を同時稼働可能ですが、100V特定負荷型では冷蔵庫(0.2kW)と照明(0.1kW)のみ対応です。
たとえば、パナソニック「Powerwall」は7kW出力で200V家電3台まで同時使用可能です。一方でシャープ「JH-RW7B2」は3.5kW出力で100V家電限定となっています。
設置環境とサイズ:追加コストが発生する場合も
蓄電池を屋外に設置する場合、直射日光よけのカバーなどが求められます。また、エリアによっては塩害対策や降雪対策として10万円前後の追加コストが発生するケースも。必要に応じて蓄電池を屋内に設置するのもポイントです。
蓄電池の運転音は35~40デシベルと比較的静かなものの、80~150kg前後の重量になるため、耐震ラック等の設置も推奨されています。それらのコストを踏まえて、蓄電池単体だけでなく、設置ケースなどの費用が追加でかかる点に注意が必要です。
寿命とメンテナンス:耐用年数と保証
先述した通り、リチウムイオン電池は6,000~12,000サイクルで寿命10~15年が相場とされています。鉛電池(500サイクル)より初期費用が高いものの、15年換算でLCoE(均等化原価)が30%安くなります。
また、蓄電池にも耐用年数があり、国税庁によると6年とされています。耐用年数が終わると、徐々に蓄電できる量が少なくなります。完全に充電しても、以前ほど長く電気を供給できなくなります。これは経年劣化が原因のためスマートフォンのバッテリーが長持ちしなくなる現象と同じです。
製品の保証期間などもしっかりとチェックすることをおすすめします。耐用年数が17年と長い太陽光パネルに比べて、蓄電池は6年とされているため、保証期間が長く、広範囲にわたる保証内容が付帯されていることが望ましいと言えます。
蓄電池を選ぶときの注意点
使用環境への適応
蓄電池の性能は、設置される環境(特に温度)によって影響を受けることがあります。高温または低温の環境で使用が予想される場合は、その条件下でも性能が保てる製品を選ぶことが重要です。
法規制と安全基準のクリア
国や地域によって蓄電池の安全性、環境への影響、使用や廃棄の方法などの規制が定められている場合がありますので、適用される法規制や安全基準を満たしているかどうかも事前に確認しましょう。
まとめ:最適な家庭用蓄電池を選ぶにはライフスタイルを振り返ろう
家庭用蓄電池の導入を成功させる鍵は、ご自身の目的やライフスタイルに最適な容量(kWh)を見極めることです。容量選定には主に以下の3つのアプローチがあります。
- 日常の電気使用量(特に夜間やピーク時)を基準にする
- 太陽光発電の発電量と自家消費量のバランスから算出する
- 停電時に最低限必要な電力量から逆算する
上記の計算をもとに、ご家庭の状況や優先順位に合わせて最適な一台を選ぶことが、後悔しない蓄電池選びに繋がります。初期費用だけでなく、長期的なメリットや安心感も考慮し、慎重に判断しましょう。
なお、蓄電池の導入を検討されている場合は、太陽光発電と蓄電池のセット導入がおすすめです。設置工事や人件費等をセットにできるため導入コストを抑えられる傾向にあるほか、国や自治体の補助金対象となる事例もあります。
さらに、自家消費の経済的メリットを増やせるのもポイントです。売電単価は年々下がっているため、太陽光で発電した電気を売るよりも自分のご自宅で自家消費する生活スタイルの方が最近では経済効果があると言えます。
もし、太陽光発電&蓄電池によるクリーンなエネルギーや、災害時の防災対策として蓄電池の導入を検討されている場合は、この機会に「0円ソーラー」のハチドリソーラーまでお問い合わせください。
ハチドリソーラーでは、お客様一人ひとりのライフプランに合わせて、最適なソーラーパネル&蓄電池容量をシミュレーションさせていただきます。¥
「太陽光発電や蓄電池の導入コストが気になる」「自分にあった蓄電池容量を計算するのが面倒くさい」とお考えの方は、ぜひこの機会にハチドリソーラーまでお気軽にご相談ください。
お客様が後悔しないよう、プロが徹底してサポートするほか、導入前後の補助金申請サポートも対応しております。
\\初期費用0円で始められる!//
太陽光・蓄電池・V2Hの導入から運用~メンテナンスまでプロが徹底的にサポート!
ハチドリソーラーブログ 一覧を見る