学校の電力を自然エネルギー100%に。ハチドリ電力とともに学びの選択肢を広げる_福岡女子商業高校

福岡女子商業高校さま
- 学校法人
- 101名〜500名

Overview
事例概要
導入前の課題
- 選ばれる学校にするため、学校の魅力を再構築したいという課題意識
- 環境や社会課題についての授業は行っていたが、議論で終わってしまい、具体的なアクションに落とせていなかった
- 電力コスト削減の必要性もあったが「安さ」だけで選ぶことに疑問を感じていた
導入の決め手
- 「電気=リアルな教材」と捉え、日常にこそ教育的価値があるという気付き
- ハチドリ電力の透明性や誠実な対応、オンラインでのやりとりでも伝わる信頼
- 単なるコスト削減にとどまらず、学びや価値観形成にもつながると感じた
今後の展望
- 生徒自身がNPOを調べて寄付先を選ぶなど、1%寄付の仕組みを活用した主体的な学びを展開
- 学校内の自治活動や教育プロジェクトの実施
- 生徒発案による新しい活動や挑戦を後押しし、“学校を実験の場”として活用していく
福岡市にある私立の福岡女子商業高校は、「挑戦を、楽しめ。」をテーマに、社会とつながるリアルな学びを重視している学校です。地域や企業との連携を積極的に行いながら、商業教育の新しいかたちを探究してきました。近年では、SDGsや環境教育にも力を入れ、教育現場から社会課題に向き合う実践を重ねています。
そんな同校が、2025年4月より、学校で使用する電力を自然エネルギー100%の「ハチドリ電力」に切り替えることを決定。日常の“電気”をリアルな教材として活用する、新たな一歩を踏み出しました。
今回は、校長の柴山翔太さんと事務長の徳永道昭さんに、導入の背景や再エネを選ぶ意味、そして学校が描くこれからのビジョンについて、お話を伺いました。
「憧れ」から始まる学びのデザイン
まずは、柴山先生がこの学校にどんな想いで関わってこられたのか、お伺いしてもいいでしょうか?

柴山さん:校長になる前から、商業高校って「もっと面白くなるはず」と感じていました。歴史のある学校ではあるけれど、時代の流れの中でだんだんと選ばれにくくなっている。でも本来、商業高校は社会と直結していて、大人が関わりやすい場所だと思うんです。
そこで、教育に「憧れ」を持ち込むというテーマを掲げて、さまざまな社会人の方に来ていただくようになりました。今では、週に一度も大人が来ないという週はないくらいです。生徒も「今日はどんな人が来るんだろう?」と自然と関心を持つようになってきました。
高校生にとって“大人と出会う”ことは、どのような意味を持つのでしょうか?
柴山さん:高校生って、人生で初めて「大人と出会う」時期なんですよね。その出会いによって、価値観や進路が大きく変わることもあります。だからこそ、ただ知識を教えるだけではなく、「こんな大人になりたい」と思えるような出会いを届けたいと考えています。
私自身、学校という場に“憧れ”を持ち込むことがとても大切だと思っています。一度でもその“憧れ”が生まれれば、気持ちに火がついて、学びは自然と動き出す。言われてやる勉強ではなく、「やってみたい」と思って始める学びを、日常の中にたくさんつくっていきたいんです。
環境教育を“日常”に落とし込む
環境やSDGsといったテーマにも、学校として積極的に取り組まれているそうですね。

徳永さん:私自身も「若いうちから社会に目を向けられる人を増やしたい」と考えてきました。商業高校は、社会や経済と最も近い場所。だからこそ、単に“稼ぐ”だけではなく、「社会にどう貢献するか」という視点も育てたいんです。
うちの学校には起業したいという生徒もいますが、起業を通じて社会をどう良くしていくかという話も、自然と入ってくるようにしています。そのために、いろんな大人を招いたり、プロジェクトを紹介して、自分で選んで関われる機会を用意しています。
たとえば、ピープルポートさんの「ZERO PC」プロジェクトに参加した際は、古くなったパソコンの廃棄ではなくアップサイクルという形で環境に配慮する選択肢に触れました。身近なものが教材になる、すごく良い体験になりましたね。
自然エネルギーの電気に切り替えることが、生徒の学びにつながる可能性
今回、電力会社を自然エネルギー100%のハチドリ電力に切り替えたきっかけは何だったのでしょうか?

柴山さん:授業の中でも、環境問題や社会課題の話がよくあがります。「電気自動車に乗っていても、その電力源が火力発電なら意味がないよね」といった議論など。でも、そうした話題で終わってしまうことも多いんです。
そんな中でハチドリ電力の話を聞いて、「これって日常そのものが教材になるんじゃないか」と思いました。特別な教材を用意しなくても、電気という“当たり前”から価値観を育てられる。それって、すごく教育的価値があると感じました。
電力の切り替えには、コスト面での課題もあったかと思います。最終的にハチドリ電力を選んだ決め手は何でしたか?
徳永さん:実際、財政的に余裕がある学校ではないので、電力会社の切り替えは検討していました。料金比較業者からの営業もありましたが、「安ければそれでいい」とは思えなかったんです。安くなる理由がはっきりしないものを選ぶことに、どうしても納得がいかなくて。
-1.jpg)
その点、ハチドリ電力さんは電気代が安くなるだけでなく(試算上では180万円の削減が見込み)、透明性が高く、電気料金の内訳や仕組みまで丁寧に説明してくださいました。しかも、すべてオンラインでの商談だったんです。画面越しでも誠実さが伝わってきて、すごく信頼できると感じました。
「電気は投票」という池田さんの言葉にも強く共感しました。電気のようなコモディティでも、“誰から買うか”という選択に意味がある。そのメッセージに背中を押されて、「ここにお願いしよう」と即決しました。
“実験の場”としての学校、教科書では学べない“リアルな教材”としての電気
今回の取り組みを通して、今後どのような学びや活動を期待されていますか?
徳永さん:ハチドリ電力の「電気代の1%を寄付できる仕組み」は、学校にとっても大きな可能性があります。たとえば、社会課題に取り組むNPOを生徒たち自身で調べて、寄付先を選ぶようなプロセスは、まさに実社会とつながる学びになる。
さらに、その寄付金を学校内の自治活動や生徒会の取り組みにも活用できるようになれば、教育活動の持続可能性にもつながります。「ラーニングバイギビング」などの活動資金にもなるかもしれません。電気代をただ支払うだけでなく、学びにつなげる発想は、他の学校にも広がってほしいと感じています。
最後に、この取り組みをどう育てていきたいとお考えですか?

柴山さん:電気って、実はすごく“リアルな教材”になると思うんです。たとえば、電力使用量やCO₂排出量を見える化して、「どうやったら減らせる?」と考えるような探究学習にもつながる。そういう活動が生まれてくることに期待しています。
大人が全部決めるのではなく、生徒自身が「こういうことやってみたい」と発案してくれるのが理想です。学校は“実験の場”だからこそ、こうした新しい挑戦を柔軟に受け入れて、どんどんチャレンジしていきたいですね。

電気を再エネに変えてみませんか? お申し込みはこちらから!
電気のお申し込み
電気の切り替えはWEBサイトから
3分ほどで完結します。
プランお申し込み
低圧、従量法人プランお申し込みはこちら
お問い合わせ
拠点が複数ある場合や高圧の法人の方は一度お問い合わせください。
よくあるご質問
自然エネルギーを証明するものはありますか?RE100の条件に満たしていますか?
トラッキング付き非化石証書や独自の証明書を発行することが可能です。RE100にも対応しています。
なぜ基本料金を大手より安くできるのですか
一般送配電事業者に支払う基本料金に利益を乗せず、原価で請求させていただいているためです。
従業員説明会は有料ですか
無料で開催させていただきます。
解約する場合、違約金はかかりますか?
いつ解約をされても違約金はかかりません。
市場連動補填金とは何ですか?
超過金額を、市場連動補填金の費用を控除した残金を上限として補填するシステムです。補填方法については法人プラン約款をご確認ください。
電気利用開始後、すぐに補填の対象になりますか?
利用開始後の翌検針月の請求から補填の対象となります。
Switch for Good
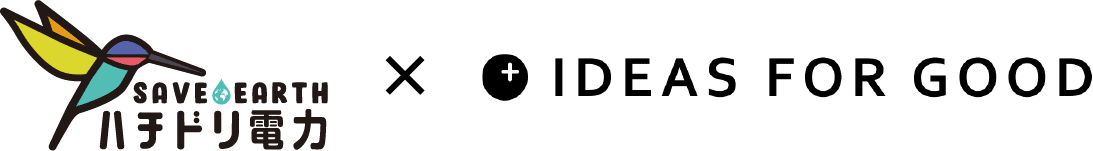
地球を想ってできたハチドリ電力と、社会をよくするアイデアを集めたマガジンIDEAS FOR GOODのコラボ企画。
ハチドリ電力を通して支援できる団体のストーリーを紹介していきます。
電気の切り替えや自然エネルギーについてお気軽にご相談ください!











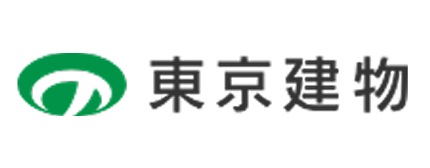

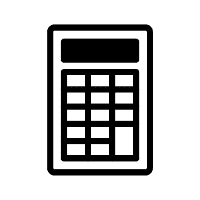

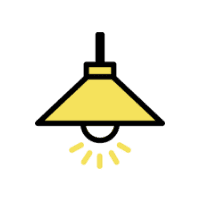

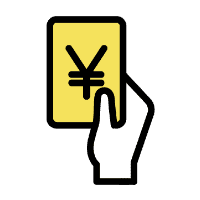
 LINEで相談する
LINEで相談する 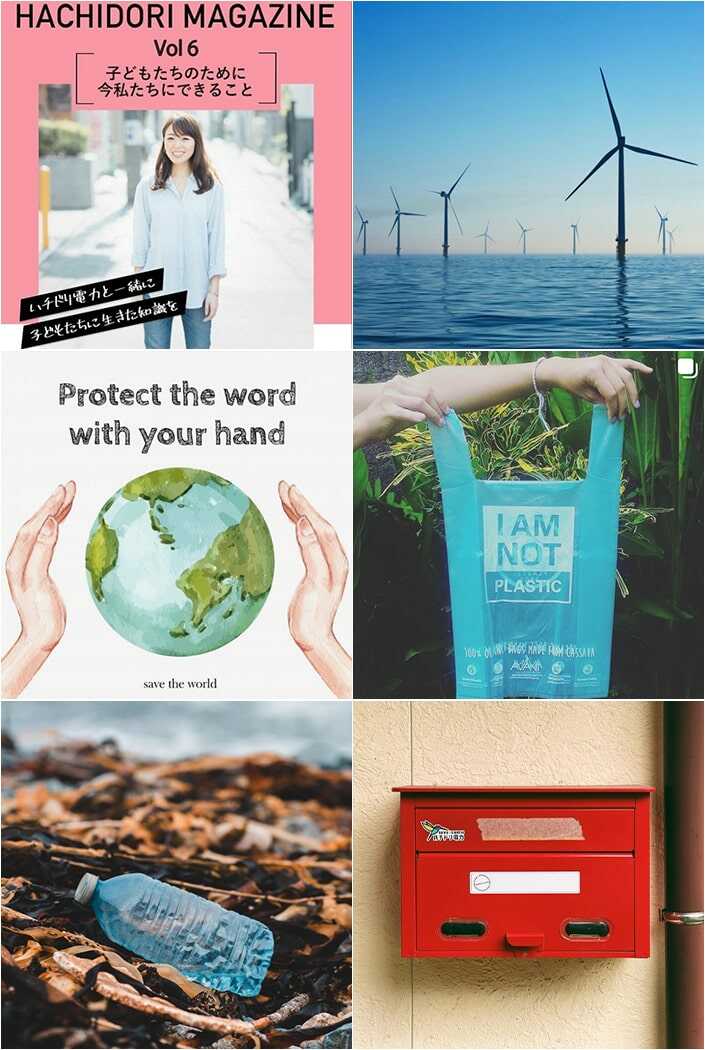

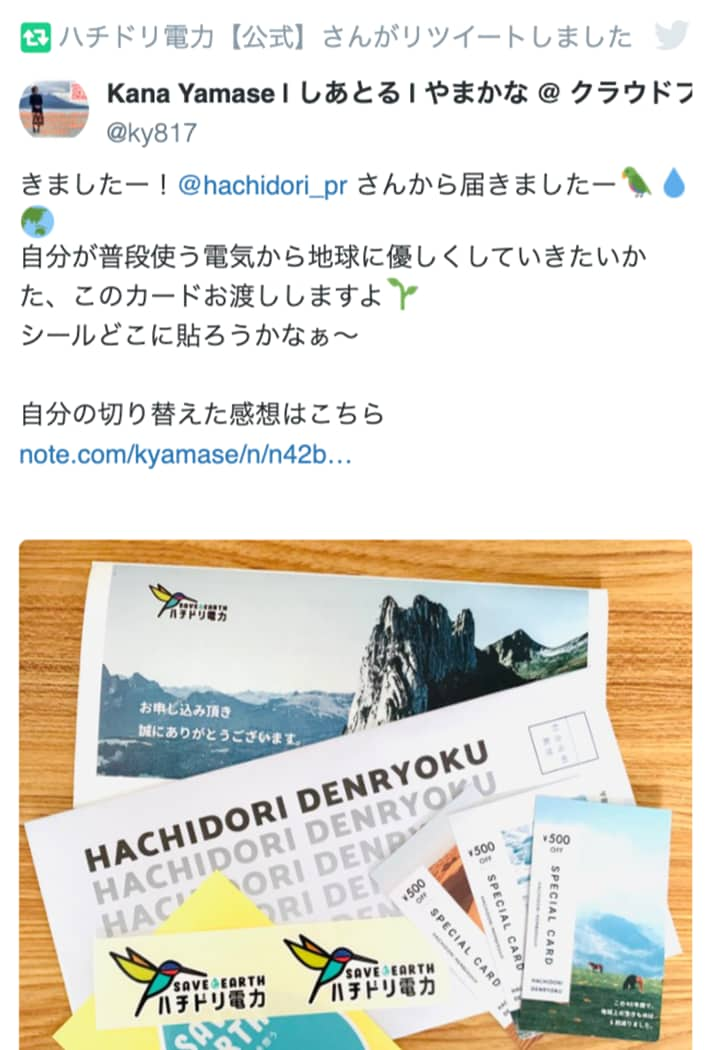


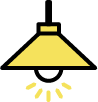

 電気で
電気で